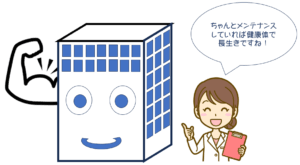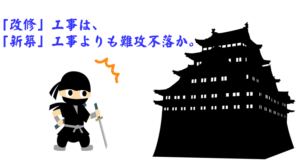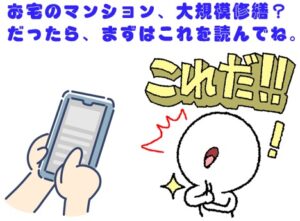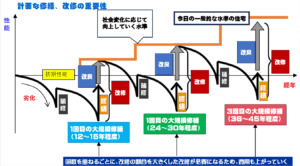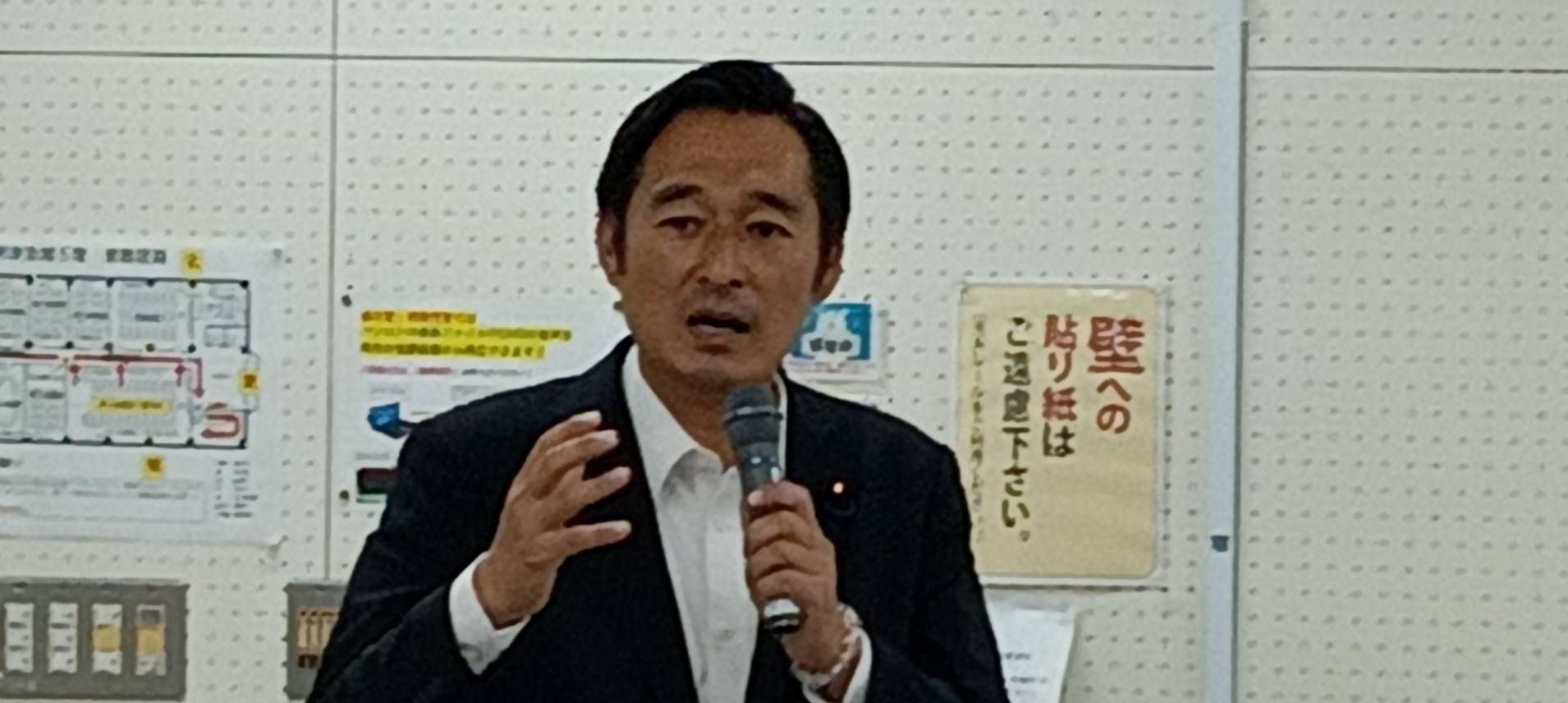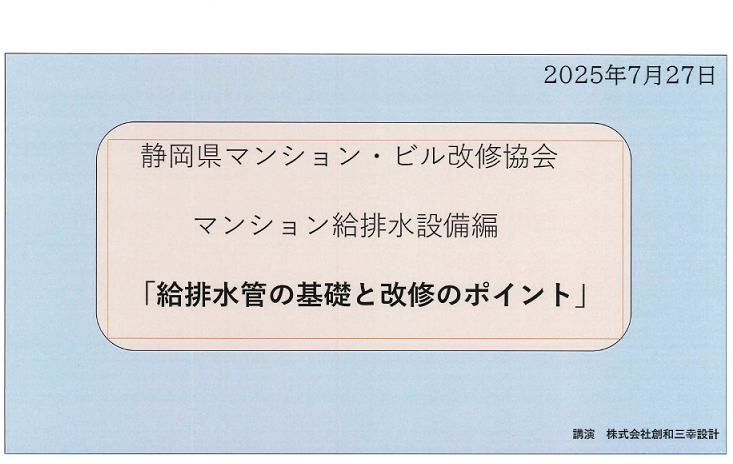マンションの大規模修繕の進め方として、設計監理方式と責任施工一括方式があります。
設計監理方式とは、設計コンサルタントに依頼して、調査・診断、設計、施工者の選定作業、施工状況の監理まで、一連のプロセスにおいて管理組合に伴走してもらう方法です。
一方の責任施工一括方式は、調査・診断、設計と、施工を一括で施工会社に任せてしまう方法です。
どちらが正しいやり方かというような話ではありません。どちらが一般的なのかと言えば、かつては責任施工一括方式が主流だったものが、しだいに設計監理方式を採用する事例が追い付いてきたといった感じでしょうか。ただ、静岡県内では、今も責任施工一括方式が圧倒的に多いように見受けられます。
これは、管理組合が主体的に携わっているか否かによっても違ってくるでしょう。平素からマンションの管理に対して管理会社に任せきりというマンションでは、大規模修繕も管理会社主導で進む流れになるでしょう。この場合、管理会社は、比較的、設計コンサルタントを入れず、普段からの信頼関係に基づく施工会社に直接発注するケースが多いのです。管理会社によっては、設計は自社で進め工事のみを外注する場合もあります。
大規模修繕を管理組合が主体的に進める場合は、組合が施工会社を選定します。複数社から見積もりを取って判断することになりますが、その前に調査・診断と、計画、設計作業が必要になりますから、設計コンサルタントに依頼する流れになるのです。
当協会は設計監理方式を推奨しています
今から「大規模修繕」をスタートしよう、そうお考えの皆様には、設計監理方式の採用を検討されてはどうでしょう。設計監理方式だと設計費が余計にかかってしまうのではとの声をよく耳にします。果たしてそうでしょうか。
設計監理方式を推奨と責任施工一括方式には、どんな違いがあり、どういうメリットがあるのかフラットな視点で考えてみましよう。
Ⅰ.設計監理方式のメリット
➀本当に必要な修繕に絞れる
専門家が建物を診断し、修繕内容を必要なものだけに絞り込むことで、無駄な工事費を抑えることができます。
➁客観的な視点で工事内容を決定
設計監理者は管理組合の意向を踏まえながら、修繕積立金の積み立て状況も見ながら、専門的見地からアドバイスを受けることができ、客観的な視点から工事内容を決定できる。
➂競争原理によるコスト削減
施工者の選定は、設計監理者が公募条件などをアドバイス、応募してきた複数社に見積もりを依頼して決定しますので、競争原理が働き、コスト削減につながることが期待できる。
➃工事の品質向上、欠陥施工の抑止
設計監理者は、工事期間中の施工状況や品質を厳しくチェックしてもらえる。
➄管理組合の負担軽減
設計監理者が、管理組合の立場で施工会社側との手続きや交渉を行ってくれるため、管理組合の負担を大幅に軽減することができる。
➅施工の契約における透明性の担保
複数社からの見積もりに基づき、皆さんが施工者を決定しますので、透明性が担保される。
Ⅱ.責任施工方式のメリット
➀設計コンサルタント料が不要
工事費の5~10%とされる設計コンサルタント料金が発生しない(調査・診断、設計は施工会社も行うので丸々の差額ではありません)。
➁管理組合などでの検討事項(計画立案、施工者選定)が少なく済む。特に、管理会社が主導してくれると、管理会社と施工会社間で進んでいくので、管理組合側の負担は極めて軽くなる。
③計画段階から一社とのやり取りになるため、窓口が絞れていて楽だ。
➃瑕疵などの問題点があった場合の責任が明確だ
ざっと並べてみました。
当協会が設計監理方式を推奨するのは、特にⅠ.の➅についてです。
大規模修繕にかかる予算は大変大きなものになりますので、トラブルの火種になりがちです。特定の1社と契約してしまうケースでは、管理会社が施工会社から、管理組合の役員の誰かが施工会社からバックマージンを受け取っているのではないかと、実際には根も葉もない話でも、そんな疑念を抱く人も現れるものなのです。
大規模修繕を契機に管理会社を解約したり、居住者間のコミュニティーが崩壊してしまったりと、昔からありがちなことなのです。管理会社にとっても管理組合にとっても、とても不幸な話です。
また、裏を返せば、実際にそういうケースが起らないとも限らないということでもあります。
したがって、施工会社の選定プロセスは透明性を担保することが極めて重要であり、そのために客観的な第三者として設計コンサルタントを採用することに大きな利点があるのです。
設計コンサルタント料がかかることは事実ですが、Ⅰ.の➀➁③のような理由で、逆にトータルコストを低く抑えることができる可能性が高いのです。
こうした理由から、当協会では、管理組合が主体的に大規模修繕プロジェクトに臨むケースでは、設計監理方式をお奨めします。
ただし、管理会社に全幅の信頼を置いているマンションや、マンション自体の規模も小さくしっかりと居住者間で意思疎通が図れているのであれば、アドバイスの範囲ではありません。